小数や分数、図形が出てくると、どう教えたらよいのかわからないし、パパは数学が得意なので、教えてくれるのはよいけれど、子どもにはパパの言っていることが難しくてわからない…など。
今回は、ご家庭で簡単にできる「算数力」アップの取り組みについてご紹介します。
学校の宿題や塾のプリントの問題を解く前にぜひやってみてください。
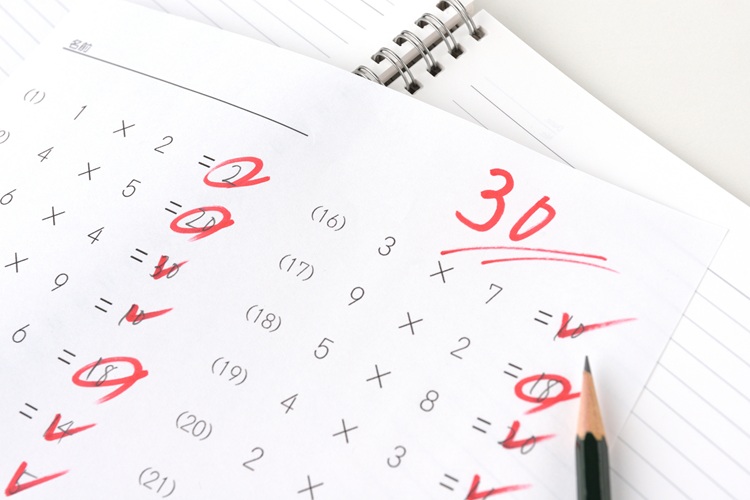
ここでは、普段の生活の中で取り組みたい、算数力を上げる方法としては、「一対一対応」を経験することをおすすめします。
お手伝いを通じて、数の基本である「一対一対応」を知ることができます。
お友だちが来る、親戚が集まるという場面で、お皿やコップを人数分用意したり、お菓子を配るといったことをお子さんと一緒にしてみましょう。
昔、豊臣秀吉が、山の木を数える時に一本一本に縄を結びつけ、後でその縄を集めて数えたという話があります。
これはまさに「一対一対応」をうまく使って多くの数を数えたエピソードといえるでしょう。
まず子どもたちには、「数は何かを数えるために発明されたものか」ということを体験的に知ってもらうことが必要なのです。
算数の勉強をするとなると、どうしても数字そのものを目にすることの方が多くなりますが、数字は「記号」でしかありません。
足すと10になる数など、計算問題が苦手な子は、いきなり「数字」を見過ぎてしまいます。
数字で計算する前に、おもちゃやお菓子で実際の数を目にして体験することが大切です。
また、繰り上がりのたし算が苦手だというお子さんも多い傾向があります。
よく目にする手の指で数える方法も、最大で10本までです。
普段の暮らしの中では、家に10以上置いてあるものも多くはありませんよね。
数が大きくなればなるほど、頭の中で想像しなくてはならなくなります。
だからこそ、想像力の手助けとなる「目で見て認知すること」「体験的に知っておくこと」が、必要となるのです。
10以上を扱う繰り上がりが理解に時間がかかるのも、もっともなことなのです。
5人の人がいたとして、前か後ろから数えて「パパ・ママは何番目?」「自分は何番目?」という質問を、お子さんにしてみましょう。
どちらから数えても全体の人数は変わりませんが、一人一人の順番は変化します。数の持っている役割が、「一対一対応」とは違っていますよね。
全体を把握し、自分の求めるもの(この場合1,2,3,4といった数字)がどこにあるか「位置を把握する力」は、算数力を高めるために重要な役割を果たします。
図形はもちろん、統計やグラフ、関数など、多岐にわたって必要となる力と言えるでしょう。
他にも数字を順番に線で結ぶと、なにか図形になる、といった遊びもよいでしょう。
また、トランプも「順序の数」を知るには素晴らしい教材です。
ハートの6ならハートが6つ描かれている、というのがよいところ。
単純なトランプゲームの「七並べ」でも、「順序の数」の理解を助けるゲームのひとつになります。
先ほどもお伝えした通り、お皿に分ける経験はおすすめです。
数えられるものばかりではなく、数えて分けられないものも分けてみましょう。
飲み物、ポテトサラダ、ホールケーキやピザなど。同じ量にすることは、子どもたちにとっては少し難しい課題です。
飲み物やポテトサラダは、おおよその目安を自分で作って多すぎたらそこから少し減らし、少ないところに足してみるなどで「ならす」ということを学びます。
平均の計算などにゆくゆくは活きる感覚をここで身につけることができるでしょう。
ホールケーキやピザ、板チョコなどを分けることは、図形や分数の学習の大元にもなります。
まだ小さいお子さんの場合、お子さん自身が分けられなくてもよいのです。
それを分けている様子を目にすることだけでも十分学びにつながるはずです。
わり算の文章問題を解いていると、「8本のペンを4人で分ける」はできても、「8本のペンを2本ずつ分けると何人に分けられるか」を分からないお子さんがけっこういます。
「幅30センチの本棚に、3センチの厚さの本は何冊並べられるか」といった問題も、同じパターンですね。
わり算は、「全体の中にそれがどのくらい含まれているのか」を導き出すものです。
それは「全体を分ける」ということをたくさん見ていればいるほど、「あ、そういうことか」とピンときやすくなるわけです。
「かたち」が苦手なお子さんの場合には、安定した形を目にすることが重要です。
正方形・立方体・長方形・正三角形・直角三角形など、折り紙や積み木で遊びながら、形に触れておきましょう。
例えば、「直角とはどんなものか」を子どもたちに言葉で説明することは難しいですよね。
けれど私たちは、「こういうものが直角」ということを体験的に知っているはずです。
折り紙の角は直角、ノートの角も直角、アナログの時計の真ん中を十字に分けるとそのひとつは直角、など説明する必要はありませんよね。
「目にしている」ということが大切なのです。
それがゆくゆくは、平面図形や立体の理解、角度の理解や分数の理解につながっていくのです。
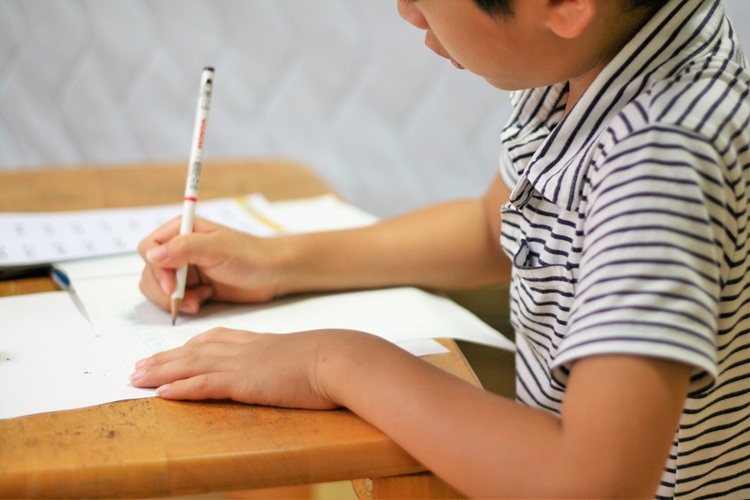
学校の授業に関して言えば、基本的に家でできるのは教わった技術の反復です。
野球で言えば、筋トレや素振りのようなものでしょうか。
極論を言えば、宿題をやってわかるようになるのではなく、授業で理解しわかったことを、宿題を通して体得するのです。
また、その時に理解できなくても、体験の積み重ねによって、以前は理解できなかったことができるようになるかもしれません。
国語力が伸びたり、他の教科の学習を通してものの捉え方に変化がおきたりすることでも、理解は深まっていくでしょう。
算数の学習はスパイラルのようになっていて、似たようなところを繰り返し通りつつ、上昇していくイメージを持っていてください。

よく、子どもが算数が苦手という場合に、お母さんが何度も「私も算数が苦手だったので」「ママも算数が苦手だったから似ちゃったのかな」とおっしゃる方がいます。
子どもの前で言うこうした言葉が、実は、お子さんのセルフイメージの形成につながっていることがあります。
ママにとってみれば、お子さんの気持ちを少しでも軽くしようと思っての言葉かもしれませんが、その子にとっては「僕は算数が苦手なんだ」という刷り込みになってしまっているということです
細かいことを言えば、本当に算数が苦手で算数の問題が解けなかったかどうかはその時点では分からないことです。
その子にとっては、先生の言葉が難しすぎたのかもしれませんし、大勢いるクラスの中で、物音や人の動きに気が散って、落ち着いて授業に取り組むことができなかった可能性もあります。
保護者の方が意識していない日常の声がけで、お子さんのセルフイメージがプログラミングされているということを頭の片隅においておきましょう。
また、どんな学び方が子どもに合っているかは人それぞれ違っているのが当たり前です。
同じ授業を聞いて、全員が同じ理解度・到達度であるはずがありません。
ひとりひとりの進み具合は違っていて当たり前なのです。
まずは保護者の方が、お子さんが「何ができて、何ができないのか」を知ることです。
どんな方法なら理解しやすいのか、どんなやり方なら取り組みやすいのかを見つけ出すことに力を注ぎましょう。

まとめ
時間がかかったとしても算数の力を支えているのは、日常の体験から学んだ、目で見て手で触って得たものに他なりません。
いつ腹落ちするのかは、一人ひとりのタイミングも違います。
楽しく学べて体得できたら、とてつもなく楽しくなるのが算数です。
ご家庭でできる取り組みをぜひ、試してみてください。

