認知症だと診断されると、原則として本人の預金が引き出せなくなります。
それは、たとえ使用目的が本人の介護費用でも同じです。
今回は、親が認知症と診断された場合の対応についてご紹介したいと思います。
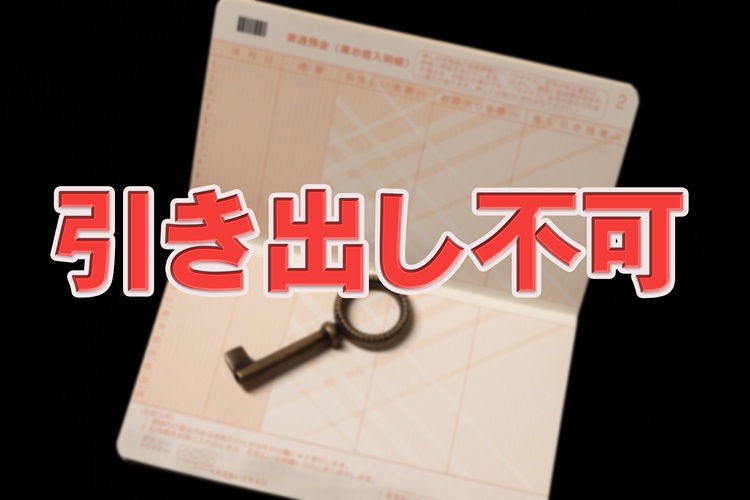
親の預金の使用目的が施設費用や介護費用であっても、本人が認知症だと原則としてお金は引き出せません。
銀行などの金融機関は、原則として口座の名義人本人とのみ取り引きを行います。
本人が高齢になり認知症などで判断能力が低下した場合、金融機関はお金の引き出しなどの取り引きを制限します。
いわゆる口座凍結です。
金融機関口座の凍結は本人の財産保護を目的としています。
たとえ本人の介護費や施設の入居費が目的であっても、本人の引き出しても良いという意思が確認できなければ、銀行は家族や親族にお金を下ろさせてはくれないのです。
全国銀行協会は、口座名義人が認知症を発症することによって、預金の払い出しや口座の解約などに支障が出るケースが増加していることを受け、2021年に認知症患者の家族が預金引き出しを求めた場合の金融機関の対応指針を発表しました。
この指針の中では、認知症患者との取り引きの一般的な対応として「親族などに成年後見制度等の利用をうながす」ことが示されています。
そのため、家族が認知症を発症して金融機関の取り引きなどに支障が生じそうな場合は、早めに成年後見制度の利用を検討する必要があると思われます。
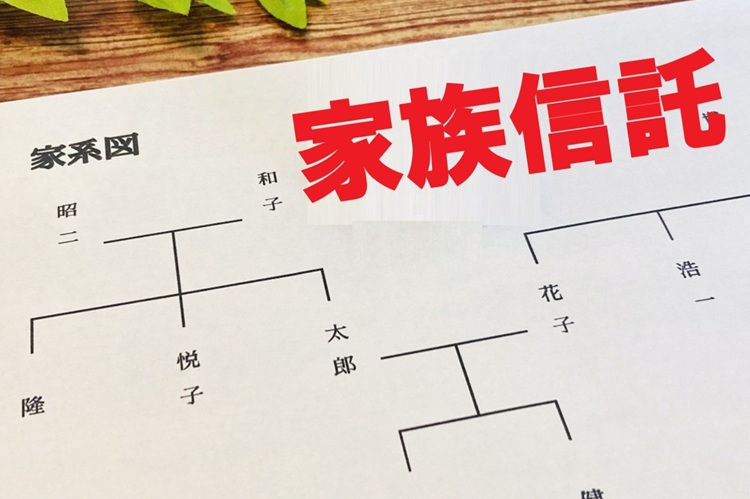
しかし、すでに認知症で判断能力が低下している場合、利用できるのは法定後見制度のみとなります。
親族などが任意代理人となって取り引きする方法もありますが、本人の意思のもと法的に認められる代理権の付与が行われており、銀行に代理権があることを届け出ている必要があります。 そのため認知症発症後に手続きするのは難しいでしょう。
応急的に家族や親族の代理が認められるケースもありますが、原則である法定後見制度を利用するには、家庭裁判所に申し立てをして、成年後見人等の選任手続きをする必要があります。
申し立てから成年後見が開始するまでに2ヶ月程度かかるケースもあり、お金がすぐに必要なときには対応することができません。
そのため、全国銀行協会の指針では、本人の判断能力が低下し、成年後見制度の利用もしていない場合に、家族や親族による取り引きを限定的に認める考えも示されています。
ただし、すべての取り引きに応じてもらえるわけではなく、医療費や介護費、生活費などといった本人の利益にとって必要な費用に限り対応するといった内容になっています。
また、全国銀行協会の指針は全ての金融機関に対応を指示するものではないため、実際の運用は各金融機関ごとに異なることに注意する必要があります。
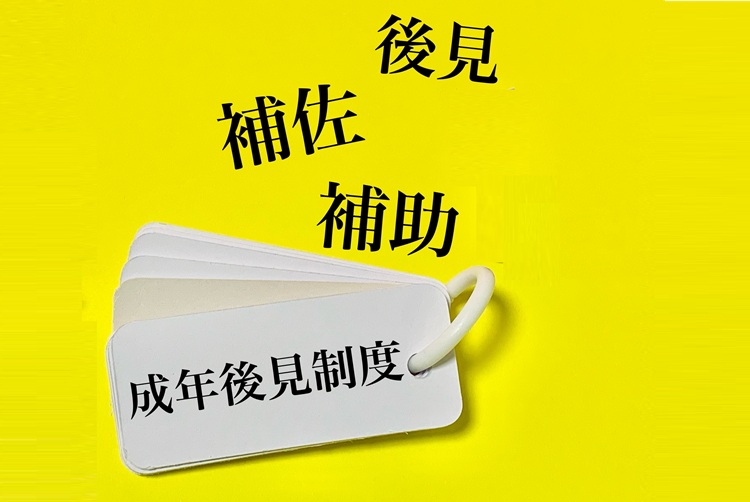
親の介護費用や施設の入居費用がいざ必要となったときに困らないように、本人が元気なうちにスムーズに財産管理ができる対策をしておくことが大切です。
主な手段としては、任意後見制度や家族信託などが挙げられます。
任意後見制度
本人の判断能力があるときに契約で任意後見人(受任者)や任せたい財産管理の範囲を契約で定めておき、本人の判断能力が低下したあとに家庭裁判所に申し立てて契約を発効させる制度。
家族信託
本人(委託者)の財産を信託財産として家族(受託者)に託し、信託契約に定めた目的に沿って管理や運用を任せる制度。
また、いざというときに財産の状況や介護方針に関する本人の希望が分からず戸惑わないようンい、普段から親とお金や介護に関する情報を共有しておくことも大切です。

まとめ
親の認知症で銀行口座が凍結されてしまえば、目的が施設の費用や医療費などの支払いであってもも、原則としては同じ対応になります。
もしも親の認知症により口座が凍結されたら、基本的には成年後見人などの法定代理人を立てる必要があります。
全国銀行協会の指針により、応急的に家族や親族でも取り引きができるケースもありますが、限定的な対応でしかありません。
やはり、親が元気なうちに家族で対策を講じておくのが大切なのです。

