直接命に係わる致命的な病気ではありませんが、胃腸、皮膚、神経機能などの一連の問題に繋がる事が多く、パンドラの箱を開けたように次々に新しい病気が見つかりやすいことから『パンドラ症候群』パンドラ症候群と言われています。
簡単に言えばオシッコが出にくい状態が続くことで、トイレ頻繁に行ったり長時間トイレで頑張ってたり時に血尿などの症状が現れる症状を指します。
今回は、猫の『パンドラ症候群』についてご紹介します。
1.頻尿(トイレの回数が増える)
排尿時の痛み(鳴く、トイレを嫌がる)
3.血尿(尿に血が混じる)
4.トイレ以外での排尿(粗相)
5.過剰なグルーミング(特に下腹部を舐める)
★ パンドラ症候群の対処法
1.ストレスを減らす工夫をする
2.トイレ環境を見直す
1.ストレスを減らす工夫をする
★ 適度に遊んでストレス発散をする
★ まとめ
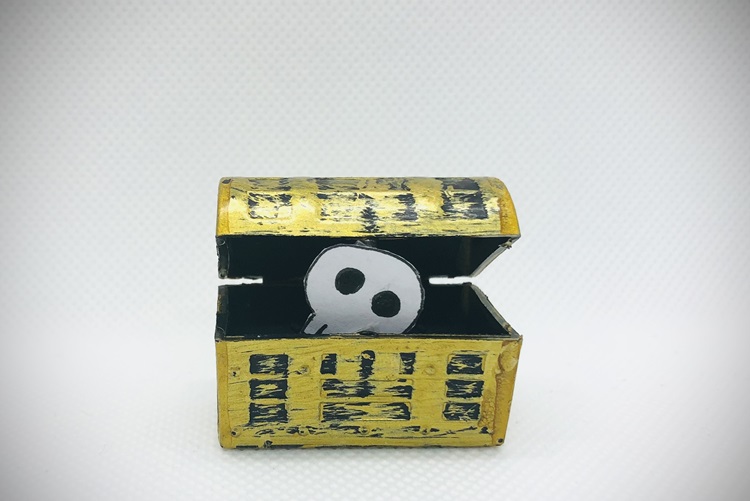
パンドラ症候群とは、猫の泌尿器のトラブルの一種で、特にストレスが大きく関係しているのが特徴です。
頻尿や血尿、トイレ以外での排尿といった症状が見られますが、細菌感染や結石といった明確な原因が見つからないことが多く「特発性膀胱炎」と診断されることもあります。
パンドラ症候群という名前の由来は、一つの原因だけでなく、環境の変化や食事、トイレの状態、飼い主との関係など、さまざまな要因が関係していることと、パンドラの箱を開けたように次々に新しい病気が見つかりやすいことから特定の治療法だけでは解決しにくいところから来ています。
パンドラ症候群の症状は、最初は他の泌尿器の病気と区別がつきにくいことがあります。
飼い主が注意して観察することで、早めに気づいてあげることが大切です。
1.頻尿(トイレの回数が増える)
猫がトイレに行く回数が増えるものの、一度に出る尿の量が少ないことが特徴です。何度もトイレに入るけれど、ほとんど尿が出ていない場合は注意が必要です。
2.排尿時の痛み(鳴く、トイレを嫌がる)
排尿の際に「痛い」と感じるため、トイレの中で鳴いたり、トイレに行きたがらなくなったりすることがあります。排尿の途中で中断するような仕草を見せることもあります。
3.血尿(尿に血が混じる)
尿の色がピンク色や赤っぽくなることがあります。トイレの砂に血が混じっていることもあるため、猫の尿の色を定期的にチェックしておくとよいでしょう。
4.トイレ以外での排尿(粗相)
これまで問題なくトイレを使っていた猫が、急にカーペットや布団、ソファの上などで排尿してしまうことがあります。
これは、トイレで排尿すると痛みを感じるため、別の場所で排尿しようとする行動です。
5.過剰なグルーミング(特に下腹部を舐める)
膀胱や尿道に違和感があるため、お腹や後ろ足の付け根を頻繁に舐めることがあります。
毛が薄くなったり、皮膚が赤くなったりすることもあるため、普段よりグルーミングが多いと感じたら注意しましょう。

パンドラ症候群は、環境や生活習慣の改善によって症状が落ち着く場合があります。
ストレスも一つの大きな要素になり得るため、猫が安心して暮らせるように、日常のケアを見直してみましょう。
1.ストレスを減らす工夫をする
猫がリラックスできる環境を整えることは、パンドラ症候群の改善につながります。
狭くて暗い場所を好む猫のために、キャットハウスやクッションのある隠れ家を用意すると安心できます。
また、引っ越しや模様替えなど環境の変化がある場合は、落ち着ける場所を確保し、少しずつ慣れさせることが大切です。
さらに、猫用フェロモン製品を活用すると、安心感を与え、ストレスを軽減する効果が期待できます。
2.トイレ環境を見直す
猫が気持ちよく排尿できるように、トイレ環境を整えることが大切です。
理想的なトイレの数は「猫の数+1個」とされており、十分なスペースを確保すると安心して排尿できます。
また、猫砂はこまめに交換し、常に清潔な状態を保つことが重要です。
さらに、猫によって好みのトイレの形や砂の種類が異なるため、様子を見ながら適したものを選ぶと、ストレスを軽減できます。
3.水分をしっかり取れるようにする
水分不足は泌尿器のトラブルにつながるため、猫が自然に水を摂取しやすい環境を整えることが重要です。
ウェットフードを取り入れると、水分を多く含んでいるため効率的に補給できます。
また、家のあちこちに様々なタイプの水の容器を置くことで、猫がこまめに水を飲む機会を増やせるでしょう。
猫のこだわりも満たせる可能性があります。
さらに、流れる水を好む猫にはウォーターファウンテンを用意すると興味を引きやすく、水分摂取の促進につながります。

猫は遊びを通じて運動し、ストレスを発散するため、適度に遊ぶ時間を作ることが大切です。
猫じゃらしやボールを使って一緒に遊ぶことで、エネルギーを発散できます。
また、キャットタワーや爪とぎを設置すると、自由に動き回れる環境が整い、運動不足の解消につながります。
さらに、フードが出てくる知育玩具などを活用すると、狩猟本能が刺激され、退屈を防ぐ効果も期待できるでしょう。
パンドラ症候群は環境を改善することで良くなることが多いですが、症状がひどい場合や長引く場合は獣医師に相談することが大切です。
尿路結石や細菌性膀胱炎など、他の泌尿器疾患との区別が必要になることもあります。
また、再発しやすい傾向があるため、定期的な健康チェックを受け、早めに異変に気づけるようにしましょう。

まとめ
頻尿や血尿、トイレ以外での排尿などの症状が見られるものの、細菌感染や結石などの明確な原因が見つからないことが多く、環境や生活習慣の影響が大きいのが特徴です。
症状がひどい場合は、かかりつけの獣医師に相談して適切な治療を受けることが大切です。
パンドラ症候群は、飼い主の工夫次第で予防や改善が可能なびょうきですので、猫が快適に過ごせる環境を整え、健康的な生活をおくれるようにサポートしてあげましょう。

