事前の施設見学をする際は、入居してから「ブラック介護施設」だったと後悔しないようにチェックポイントとに目を光らせましょう。

身内あるいは自分自身が入居する際には本当に安心できる介護施設を選びたいところですが、どうすれば「ブラック介護」が横行する危険な老人ホームを見分けることができるのでしょうか。
実際に施設を見学に行かずに入居を決めるというのは無謀なことは言わずもがなですが、見学に行った時に必ずチェックすべきポイントがあります。
見学する施設に到着したら、まず施設の入り口や壁を見ます。
そこに何もなかったら良心的な施設とはいえないかもしれません。
良い施設だと、例えば『苦情ボックス』のようなものが置いてあり、利用者や家族の声をくみ取っていることが多いです。
また、利用者や家族の意見や要望にどう対処したかを、家族が来た時にそれが見やすい場所に掲示してあります。
そうした情報公開が何もなされていない“閉じられた”施設は危険だと言えるでしょう。
施設によっては定期的に利用者家族の懇談会が開かれているところもあります。
そういった会の催しも“開かれた施設”かどうかの目安になります。
ロビーに施設を見渡して、催事やイベントの楽しそうな写真が飾ってあれば、普段の雰囲気を知るうえでの参考になるでしょう。
施設案内が始まったら、まず廊下を歩く際に、天井を注意して見ましょう。
「入居者の自由」を理由にいて監視カメラが設置されていない施設は要注意です。
というのは、「自由」というのは安全が確保されてこそであり、施設の事故防止のために必要な監視カメラが設置されていない場合は、安全配慮に欠ける施設の可能性があるからです。
次に入居者がいるフロアに足を踏み入れたら、視覚だけでなく、嗅覚も使って確認しましょう。
ロビーや玄関口ではわかりませんが、フロアや入居者の居室からアンモニア臭などが漂っていれば、排泄物の処理などが適正に行なわれていない可能性があります。
入居者の入浴がおろそかにされているために、体から臭っていることも考えられます。
これは、衛生管理や消臭がきちんとできていないというケースです。
入居者の共用スペースが臭ければ、居室を開けっ放しで排泄介助をしているなど、入居者のプライバシーも守られていない可能性もあります。
入居者自身の「臭い」について言えば、口臭も重要なポイントになります。
実際に入居している方と話した時に、口臭がきつければ、口ケアが丁寧にされていない可能性があります。
口腔ケアは今、高齢者の健康問題のカギとして注目されており、食後にしっかりとケアしないと、食べ物の残滓が誤って肺に入って肺炎を起こしてしまう確率が高まります。
肺炎は高齢者にとって命取りになる病気ですし、きちんとした口腔ケアを行うことは、認知症予防にも効果的だといわれています。
お口のなかはキレイなことが望ましいですが、逆に、キレイだから良くないこともあります。
入居者の居室を見た時に「何もなくてキレイ」なのは怪しいと思ってください。
例えば、転倒の危険があったり、徘徊してしまうような入居者の部屋の床には、ベッドの下にワイヤレスのマットを置き、それを踏むとナースコールなどで知らせる対策装置(離床センサー)を使用している施設があります。
また、居室を見学した際に、壁の飾りや置いてある物などに、その人らしい部屋づくりを見ることができれば、個性や生き方が尊重されていることの判断材料にもなります。
どの部屋も画一的で、ベッドと食事台など最低限のものが置かれているだけの殺伐とした雰囲気なら、入居者ひとりひとりが大切にされていない可能性があります。
実際に入居者に介護を施すのは施設の建物ではなく介護職員なので、介護職員の見学者への対応が悪ければ、最悪、入居者が虐待を受けていることにもつながりかねません。
いくら施設の建物がきれいでも、そこで行なわれている介護の質が悪ければ意味がないので、介護を提供する職員が働く環境がどうなっているのか、介護現場の雰囲気をしっかり見ておく必要があります。
一度の見学で介護現場の実態をチェックするのは難しいですが、見学の際に職員にこと細かに質問することで見えてくるものがあります。
こちらの細かい質問に、職員がひとつひとつ丁寧に対応してくれるかどうかがポイントのひとつです。
面倒臭がらずに答えてくれるかどうかは、入居者に対するひとつひとつのケアが丁寧なのかどうかの判断材料につながるからです。
もちろん見学者や入居者への丁寧な対応や言葉づかいも、“その時だけ”の可能性はあります。
そこでチェックしたいのが、職員同士の会話です。
見学者に対してはよそ行きの顔をしていても、見学とは関係のないところにいる職員同士の会話には“素”が出やすいからです。
職員同士が横柄な口のきき方をしているようなら、入居者に対しても横柄な態度を取っている可能性があります。
もう一つよく見てほしいのは職員の表情です。
楽しそうに働いているか、疲れてしんどそうなのか、いっぱいいっぱいの状態で顔色が悪いようなら、働く環境が相当悪いと思ってよいでしょう。
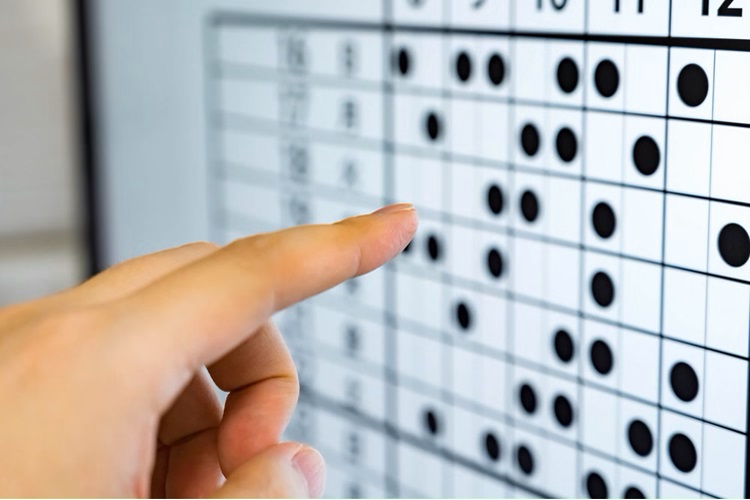
老人ホームは慢性的に人手不足に陥っているところが多いので、職員への質問に「夜間は何人勤務体制か」を入れることと、できれば事務室の出勤札やシフト札をさり気なく確認することを行ってください。
入居者15人に対して2人の夜間体制ならある程度しっかりした対応をしてもらえますが、それ以下のところは安心して任せられる施設ではないかもしれません。
また、見学する上で、職員の対応をチェックする上で有効なのが、見学時間を「午前11時半」からに設定することです。
なぜなら食事中の風景を見ることができるからです。
自分で食べられない入居者の場合、職員が横について、きちんと口元まで持っていく食事介助が基本ですが、なかにはテーブルの片側に2~3人を座らせて、向かい側から機械的に一口ずつ順番にエサを与えるように食べさせるケースがあります。
これでは入居者が喉に食べ物をつまらせてしまう確率が高くなりますし、食事自体を楽しむのとは程遠くなってしまいます。
また、赤ちゃんがするようなエプロンを平気でつけさせている施設もありますが、入居者を大切に考えているなら、タオルかナプキンをかけるなどの対応をしているはずです。
そうした施設では、効率優先で入居者の尊厳は二の次という感覚が当たり前になっているかもしれません。
食事中に、入居者同士、入居者と職員が親しく話しているかも重要なポイントです。
明るい雰囲気の施設なら問題はないが、雰囲気が暗く、入居者が無表情で黙々と食べているようならかなり心配なところです。
細かいことですが、その際には、車いすで食事している人の、車いすの汚れにも注目してください。
車いすのすき間に食べかすがこぼれたままになっていないか、埃がたまっていないか。あとはタイヤの圧がしっかりはいっているかも確認してみましょう。
車いすの空気が抜けた状態のままになっていれば、ケアが行き届いていない証拠です。

介護職員の労働環境の良し悪しは、その老人ホームを経営している運営会社の経営方針によるところが大きいので、施設そのものより運営会社を見極めることが何よりも大切です。
ホームページの謳い文句をそのまま鵜呑みにするのは危険ですし、ネットの口コミもアテにはなりません。
口コミサイトは広告が絡んでいることもありますから、それよりも施設の近くのお店とか、タクシーの運転手さんからの情報の方を重視するようにしましょう。
もし地元のタクシー運転手が施設の場所を知らないようなら要注意です。
その施設への来訪者が少ない、つまり家族や地域住民によるボランティアが出入りしていない閉鎖的な施設だと考えられるからです。
ホームページやパンフレットなどに、大げさな謳い文句を掲げている施設も疑ってみたほうがいいです。
『入居者の天使のような微笑みが我々の喜びです』とか『我々は100%の献身に何よりも喜びを見出します』とかいうポエムみたいな経営理念を打ち出している施設は気をつけましょう。
そういう経営者は何か問題があった時に、職員に対して精神論や根性論を振りかざして乗り切ろうとしがちで、パンフレットや事前説明会などが、むしろサバサバしたところのほうが信用できたりします。
本当に良い施設は、向こうのペースではなく、こちらのペースで見学させてくれます。
運営方針も熱心に語ってくれるので、45分以下ではほぼ絶対に終わりません。
1時間以上、大型施設では3時間かかることもあり得ます。
玄関に活け花が活けてあったり、食堂のテーブルに一輪挿しが置かれていたり、壁に絵画が掛けてあったりするのは良い施設の判断材料になります。
植物を枯らさない施設は人間も大事にしているし、動物を大切に飼っている施設も同様です。
「うちの職員です」と言って、スタッフとワンちゃんが一緒にお出迎えしてくれる施設などは、和やかでよい雰囲気の施設と言えるでしょう。
また、施設で生活するうえでは、食事の内容も大切な要素となります。
おすすめなのは、やはり自前で食事を作っている施設です。
決して高級和食である必要はなく、月1度のカップラーメンとか、年に1回はすいとんや流しそうめんをするとか、バラエティーに富んだメニューで家庭の延長になっているところがおすすめです。

まとめ
長くお世話になる可能性もるので、入居を検討する際は、入居希望者に合った良い施設かどうかを、付き添う見学者も一緒に見極めたいものです。
怪しい老人ホームチェックリスト10
1.45分以上の見学をさせてくれない
2.入り口に苦情ボックスがない
3.地元のタクシー運転手が場所を知らない
4.フロアに尿臭が漂っている
5.車いすのタイヤの空気が抜けている
6.居室が「何もなくてきれい」
7.入居者には丁寧だが、職員同士は横柄
8.食事のときに職員の付き添いがない
9.夜間のシフトが入居者15人以上に職員1人
10.HPに大げさな謳い文句が載っている

