受験勉強や資格試験など、合格に向けて勉強しているのになかなか成果に結びつかないことはありませんか。
頑張っているのに結果が出ないのはなぜなのでしょうか。
今回は、東大カルペ・ディエムの布施川天馬氏の『自分にあった方法が見つかる! 勉強法図鑑』より、が布施川天馬氏目線で努力が実を結ぶ勉強法をご紹介します。

私が高校生の頃は、私を含めた大半が「勉強は嫌い」と答えていたように記憶しています。
しかし東京大学に進学すると、ほとんどの同級生いわく「勉強は好き」。
私自身も、1年半の受験勉強を経て「勉強も悪くないな」と考えるようになりました。
同じ高校生なのに、勉強が好きな子と嫌いな子がいる。
中には私のように、嫌いから好きへと変化した人もいる。
この違いはいったいどこから来ているのでしょうか?
もちろん、東京大学に進学するような学生は勉強に耐性があるとか、進学校に通っている人は勉強に慣れているなど、さまざまな理由が考えられます。
その中で、私が考えたのは「勉強のやり方が違うから」でした。
勉強が嫌いな学生は、「結果が出にくい勉強法」ばかりやっているから、やりがいを感じにくいのではないでしょうか。
逆に、勉強が好きな学生は「結果が出る勉強法」を用いて、「やればやるほど成績が上がる」上昇のスパイラルに乗っているからではないでしょうか。
実際に私が使っていた勉強法を2つご紹介します。
勉強法の1つ目は「ゴールから逆算する勉強法」です。
これは、やるべき内容をすべて概算してから、スケジュールを確定させる考え方です。
受験は「どれだけ頭がいいか」「どれだけ多く勉強したか」を競うレースだと考えてしまいがちですが、実はそうではなくて「試験本番で合格点が取れる状態に自分を仕上げる」ゲームだと考えています。
納期までに仕事を達成できるかを問うゲームだと言い換えてもいいかもしれません。
どれだけ頭がよくても、試験で合格点が取れなければ意味がありません。
逆に言えば、志望校に合格できるだけの学力がすでにあるのなら、受験勉強なんて必要がありません。
「受験勉強」は、設定したハードル(志望校の難易度)に対して、自分の実力を押し上げるための手段なのです。
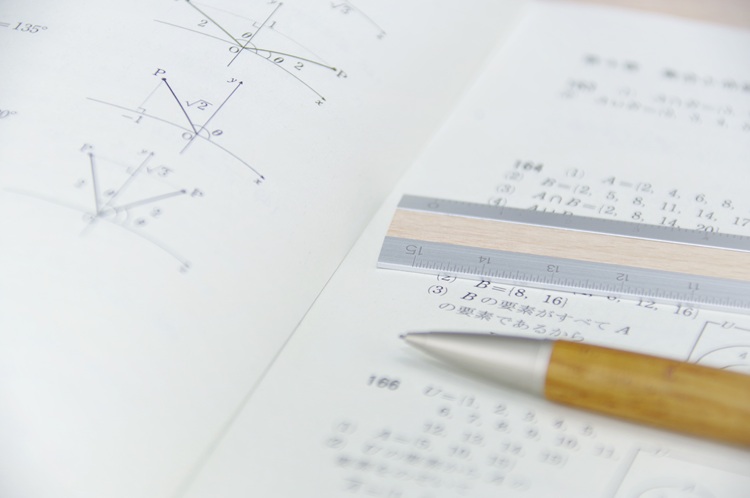
自分の実力を押し上げるためには「試験本番で合格点が取れる理想の状態の自分」と現在の自分とを比べて、足りない能力を考えます。
そして、それらの能力を習得するために必要な参考書、ドリルなどをリストアップします。
こうすれば「一覧にした本をすべて終えれば、志望校に受かる」とも考えられますよね。
これで、終わりのないレースである受験の「終わり」が見えるようになりました。
あとは、タスクが全部終わるようにスケジュールを切っていけばよいのです。
それだけで、志望校に受かるレベルにまで持っていけます。
これは、大学受験のみならず、ありとあらゆるテストでも応用できます。
すべてのテストは「目標点数を取れるか否かを競うゲーム」なのです。
「目標達成するために必要な能力」から、やるべきトレーニング内容を逆算していきましょう。
仮に、「やるべきこと」が見えなければ、合格者などから「なにをすべきか」を聞き出すといいでしょう。
聞くときに、同時に「なにをすべきでないか」も聞けると、時間を無駄に使わないで済むかもしれません。
さて、ここでお気づきになった方も多いと思いますが、これは、社会人になってからも使える「目標を立てる」際の基本となる考え方です。
東大に合格するような学生たちは、「結果を出す」意識が高校生の頃から根付いているからこそ、東大受験でも勝ち抜けるのかもしれません。
勉強法の2つ目は、わからない問題で時間を使いすぎないことです。
学生のころ、わからない問題に対して、30分も1時間も考え込んだことはないでしょうか?
あまりに長い時間考えてもわからないと「結局考えても答えは出ない」となってしまい、勉強そのものが嫌になるでしょう。
「まずは自分で考える」ことが美徳とされがちですが、「目標点数を取れる自分になる」のであれば、必要以上に考え続けても意味がありません。
「わからない問題に対して考え続ける」ことから得られる経験値には、限界があります。
結局、問題を解く目的は「その問題が解ける自分に成長すること」です。
1つひとつの問題それ自体には、大した意味がありません。
個々の問題に設定されたゴールとは、「答えに至るまでの考え方をマスターすること」であって、「問題を自力で解くこと」ではないのです。

結果が出る勉強法は、「手が止まって5分が経ったら、答えを確認してしまう」ことです。
思考の袋小路に入り込んだと判断できた時点で、切り上げて、「答えを確認してから、『なぜそのように答えられるのか』を考える」ようにしましょう。
そうすることで、問題を解く数を増やすことができます。
もちろん、1つの問題について粘り強く考え続けるのも、必須のスキルです。
試験では初見の問題が出るため、わからない問題に突き当たっても、合格点をもぎ取る努力を続ける必要があります。
大学に進学してから、社会に出てからは「答えが一意に定まらない」問題と出会う機会も増えるでしょう。
答えがある多くの問題をこなした経験や、それを解くための考え方などは、答えがない問題について考えるときにも有効に使えます。
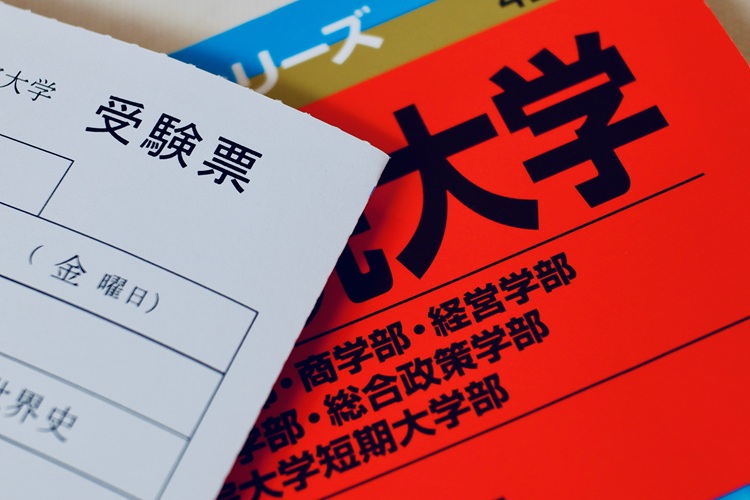
まとめ
あくまで「試験で合格点をとるために有効な勉強法」ですので、勉強の本質とは、少し離れた部分もあるように感じられるかもしれませんが、このように勉強すると合格する可能性が高まりやすいのです。
みなさんの目標達成をサポートできたようでしたら幸いです。

